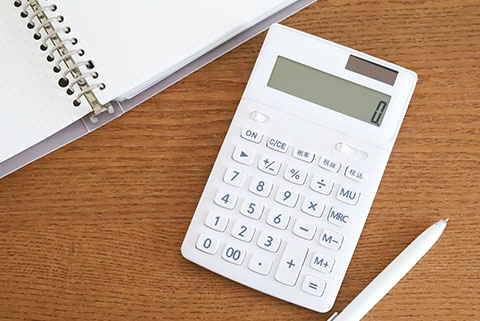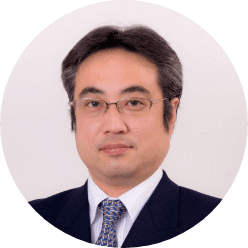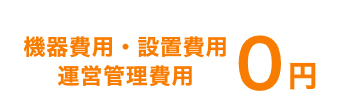駐車場の相続税評価とは
相続が発生した際には、相続税を計算するため、被相続人(亡くなった方)が残した財産にどれほどの価値があるか、1つずつ評価する必要があります。これを「相続税評価」といい、評価によって決まった相続財産の価額を「相続税評価額」といいます。
相続した土地についても同様に評価を行いますが、駐車場の相続税評価は、駐車場の種類や状態によって異なります。相続税評価額が高いほど、納税する相続税も増える可能性が高くなるので、「自分の場合はいくらになるのだろう」と不安な方も多いのではないでしょうか?
しかし、本来の相続税評価額が高くても、一定の条件を満たしていれば「小規模宅地等の特例」をはじめとする相続税の軽減措置を受けられます。
そこで今回は、土地所有者が運営する貸駐車場と、土地の賃借人(駐車場運営会社等)が運営する貸駐車場、2つの場合の相続税評価についてそれぞれ解説します。また、相続税評価が減額される小規模宅地等の特例が適用される条件も紹介しますので、ぜひ参考にしてください。


土地所有者が運営する貸駐車場の相続税評価と特例
貸駐車場の相続税評価は、運営する主体が土地所有者の場合と、土地の賃借人(駐車場運営会社等)の場合とで異なります。ここではまず、土地所有者が運営する貸駐車場の相続税評価と、特例の要件について見ていきましょう。
相続税評価
土地所有者が運営している月極駐車場等の貸駐車場は、「自用地(所有者自身が利用する土地)」として評価されます。つまり、他人に車の保管場所として土地を貸していても、賃借権の価額を控除した一般的な借地の評価とはなりません。この理由は、「車両の保管を引き受ける」という契約内容になり、土地の利用そのものを目的とした賃貸借契約とは本質的に異なる契約関係にあるためです。
また、登記簿上の地目(土地の種類)が「宅地」であっても、相続税評価上の地目としては「雑種地(どの地目にも当てはまらない土地)」として評価します。そのため、相続税評価は近隣の類似した土地の評価額をもとに、位置や形状などの条件の差を考慮して評価します。
特例の要件
土地所有者が管理する貸駐車場では、以下の条件を満たすと「貸付事業用宅地等(貸付事業のために使われていた土地)」と見なされ、小規模宅地等の特例を受けられます。
・アスファルト舗装やコンクリート舗装などの構築物がある
・もとの所有者(被相続人)が亡くなる前まで3年を超えて貸し付けている
まず、更地には小規模宅地等の特例は適用されません。そのため、アスファルト舗装やコンクリート舗装が施されておらず、土が一部露出しているような駐車場は貸付事業用宅地等と見なされないので、何らかの構築物が必要です。砂利敷きの駐車場は判断が分かれ、砂利が全体に敷き詰められ、ロープや車止めにより1台ごとの駐車スペースが区分されているものであれば、貸付事業用宅地等に見なされる可能性が高いといわれています。
また、土地所有者であった被相続人や生計を一にする家族が、相続の開始前3年を超えて相当の対価で貸し付けており、かつ、その土地を取得した相続人が相続税の申告期限までその貸付事業を継続している必要もあります。ただし、事業的規模(駐車場だけなら50台以上)の貸駐車場の場合は、3年を超えていなくとも構いません。
上記の要件を満たした場合、200㎡を限度として50%の評価額軽減を受けられます。


駐車場運営会社等が運営する貸駐車場の相続税評価と特例
土地の賃借人(駐車場運営会社等の事業者)が貸駐車場を運営している場合は、土地所有者が運営している場合とは評価が異なります。ここでは、賃借人が土地所有者から土地を借りて運営している駐車場について、相続税評価と特例の要件を見ていきましょう。
相続税評価
賃借人が運営する駐車場の場合、土地所有者は駐車場運営業者等に土地を貸しているため、土地に賃借権が付帯しており、賃借権の相当額を控除して相続税評価額が計算されます。また、相続税評価上の地目は「雑種地」です。この場合、まずは賃借権の評価から行います。
賃借権の評価方法は、「地上権」に準ずる賃借権か、それ以外の賃借権かという2つに分けて評価します。地上権とは、他人が所有する土地を使用できる権利のことです。借地権(賃借権)と似ていますが、地上権は「物権」といい、物や権利を直接支配できる権利なので、土地所有者の承諾なしで土地を貸したり、建物を建築・売却したりできるという点が借地権(賃借権)とは異なります。
地上権に準ずるものとして評価されるうえで必要な条件のうち、代表的なものは以下の通りです。
・賃借権の登記がされているもの
・設定の対価として権利金や一時金の支払いのあるもの
・堅固な構築物の所有を目的とするもの
ただし、これら全てを満たしている必要はなく、このなかに該当するものがあれば地上権に準ずる賃借権として評価されます。また、上記の条件以外でも、地上権に準ずる借地権に該当するものもあります。評価額の具体的な計算方法は、
こちらをご覧ください。
特例の要件
駐車場運営会社等が運営する貸駐車場でも、要件を満たせばその土地について小規模宅地等の特例を受けることは可能です。具体的には、200㎡を限度として50%の評価額軽減を受けられます。
また、小規模宅地等の特例の適用要件である「構築物等があること」については、土地所有者の所有である必要はなく、駐車場運営会社等が所有する構築物でも構いません。


小規模宅地等の特例に必要な条件
小規模宅地等の特例を受けるには、「貸付事業用宅地等」に該当する土地であることが第一条件です。また、前述の被相続人と被相続人と生計を一にする家族が遂行すべき事業の継続性についての要件を満たしていることを前提に、以下の要件は同じです。
・アスファルト舗装やコンクリート舗装などの構築物がある
・もとの所有者(被相続人)が亡くなる前まで3年を超えて貸し付けている
アスファルトやコンクリート舗装以外に、精算機やフラップ板、電灯などが設置されている場合も、構築物があるという要件に当てはまります。ただし、砂利敷きに関しては注意が必要です。砂利が構築物として認められるかは判断が分かれるところで、もし構築物と認められとしても、定期的に砂利を敷き直さないと構築物とは見なされないことがあります。


賃借権(借地権)の評価方法
駐車場運営会社等が貸駐車場を運営している場合には、賃借権(借地権)の相当額を控除して相続税評価額が算出されます。そこで、ここでは賃借権相当の評価方法について解説します。
賃借権の評価は前述の通り、地上権に準ずる賃借権か、それ以外の賃借権かという2つに分けて評価されます。
地上権に準ずる賃借権の場合
地上権に準ずる場合、賃借権の評価額は「自用地としての評価額×賃借権の割合」で算出します。賃借権の割合には、賃借権が地上権であるとした場合の法定地上権割合、あるいは借地権とした場合の借地権割合のうち、いずれか低いほうの割合を用います。
このうち、賃借権が地上権であるとした場合の法定地上権割合は、以下の一覧表の通りです。
| 賃借権の残存期間 |
法定地上権割合 |
| 10年以下 |
5% |
| 10年超15年以下 |
10% |
| 15年超20年以下 |
20% |
| 15年超25年以下 |
30% |
| 25年超30年以下および地上権で存続期間の定めのないもの |
40% |
| 30年超35年以下 |
50% |
| 35年超40年以下 |
60% |
| 40年超45年以下 |
70% |
| 45年超50年以下 |
80% |
| 50年超 |
90% |
一方、借地権割合は、以下の一覧表の通りです。この表は、地域ごとの路線価図の上部に掲載されています。
| 記号 |
借地権割合 |
| A |
90% |
| B |
80% |
| C |
70% |
| D |
60% |
| E |
50% |
| F |
40% |
| G |
30% |
地上権に準ずる賃借権に該当しない場合
地上権に準じない賃借権の評価は、法定地上権割合の2分の1に相当するとされます。この場合、借地権割合は計算に含まず、法定地上権割合のみを用いて評価します。


地上権に準ずる賃借権の目的とする雑種地の評価
地上権に準ずる賃借権の目的となっている雑種地の評価は、次の2つの式によって得られる価額のうち、いずれか低いほうを評価額とします。
1.自用地評価額×(1-法定地上権割合または借地権割合のいずれか低い割合)
2.自用地評価額×(1-賃借権の残存期間に応ずる割合)
賃借権の残存期間に応じた割合は、以下の表で参照できます。
| 賃借権の残存期間 |
割合 |
| 5年以下 |
5% |
| 5年超10年以下 |
10% |
| 10年超15年以下 |
15% |
| 15年超 |
20% |
上記の1の評価額は、前述の地上権に準ずる賃借権の評価額と同じになります。また、上記の1と2に用いられている割合のうち、最も高い割合を採用したものが最も低い評価額です。
地上権に準ずる賃借権以外の賃借権の目的とする雑種地の評価
地上権に準ずる賃借権以外の賃借権の目的となっている雑種地の評価は、次の2つの式によって得られる価額のうち、いずれか低いほうを評価額とします。
1.自用地評価額×(1-法定地上権割合の2分の1に相当する割合)
2.自用地評価額×(1-賃借権の残存期間に応ずる割合の2分の1に相当する割合)
上記の法定地上権割合と、賃借権の残存期間に応じた割合の2分の1の割合を用いて、評価額を計算します。
相続税評価で見る一括借り上げ方式の貸駐車場の評価
一括借り上げ方式で駐車場事業者に運営・管理を任せる場合、賃借人が貸駐車場を運営することになります。そのため、土地の賃貸借と見なされ、賃借権の相当額を控除して相続税評価額が計算されます。
賃借権の評価額の計算は、先に挙げた通り、地上権に準ずる賃借権となる要件を備えているかどうかを見て判断します。しかし、一括借り上げ方式による貸駐車場の場合、該当することはほぼありません。
なぜなら、賃借権登記や権利金の発生、堅固な構築物の所有を目的とするなど、地上権に準ずる賃借権として認められる要素がないためです。また、地上権のように強い権利があると、土地所有者が次の土地活用に転用しにくくなるほか、事業者側も賃借権登記や地上権取得のための一時金の発生といった費用面などから地上権に準ずるような賃借権を望まないという事情もあります。従って、地上権に準ずる借地権以外の借地権での評価となることが一般的です。
たとえば、敷地面積200㎡、自用地としての評価額が8,000万円、賃借権の残存期間が12年の場合、以下のような賃借権の評価額になります。
<例>地上権に準ずる賃借権に該当しない借地権の場合
・小規模宅地等の特例による評価減
200㎡まで50%の評価減となるので、評価額は4,000万円(8,000万円×50%)
・地上権に準ずる賃借権に該当しない借地権の目的となっている雑種地の評価
[1]4,000万円×(1-10%×1/2)=3,800万円
[2]4,000万円×(1-15%×1/2)=3,700万円
1および2のいずれか低い額を用いるので、3,700万円が賃借権評価額控除後の相続税評価額となります。
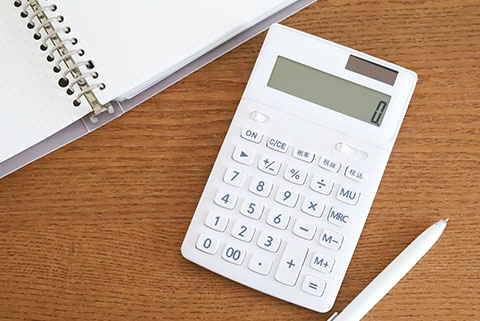

駐車場の相続税評価に関するお悩みは、三井のリパークへ
駐車場における相続税評価額は、駐車場の運営を誰が行うかによって受けられる控除が変わります。土地を駐車場運営会社に貸し出す一括借り上げ方式でも、賃借権相当額の控除を受けられるため、相続税評価額が気になる方でも安心です。
三井のリパークでは、一括借り上げ方式での駐車場運営サービスを提供しています。(※1)一括借り上げ方式では、駐車場に空きがあっても毎月一定の賃料をお支払いするので、経営リスクが気になるオーナーさまも安心です。また、相続税評価に関してお悩みの場合は、税理士のご紹介も行っています。駐車場の相続や経営に関するご相談は、ぜひ三井のリパークまでお問い合わせください。
●駐車場運営についてのご相談・お問い合わせは
こちら※1 立地等によってはお受けできない場合もございます。また、建物解体、アスファルト舗装、外構、固定資産税などの租税公課や町内会費はオーナーさまのご負担となります。