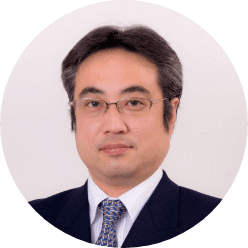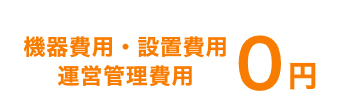定期借地権とは?
定期借地権とは、1992年の借地借家法改正によって定められた比較的新しい権利で、限られた一定期間だけ土地を借りることのできる権利を指します。更新がなく、契約期間が満了すると、原則として土地は更地に戻して土地の所有者に返還する必要があります。一定期間経過すると更地になった土地が戻ってくるため、普通借地権と比べて土地所有者が貸しやすいことが特徴です。
そもそも借地権とは、「建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権」(借地借家法 第一章 総則 第二条)のことで、この借地権のなかに定期借地権も含まれます。「建物の所有を目的とする」ため、建物の建つ土地または建物を建てる予定のない土地に借地権は設定できません。
なお、借地権は定期借地権と普通借地権に分類され、それぞれ異なる特徴を持っています。
1992年の借地借家法改正以前の借地権は、借地人(借主)の権利が強く保護されていました。しかし、借地借家法の改正で登場した定期借地権は、土地所有者(地主)が強く制限されていた返還の権利を主張できるようになり、特に土地所有者にとってはより柔軟で計画的な土地利用が可能になりました。コンビニ、飲食店、病院、倉庫など私たちの日常を支える施設から、ショッピングモールやアウトレットモールといった大規模な商業施設のほか、一等地のマンションに至るまで、定期借地権の設定によって幅広いケースで活用されています。前述のように定期借地契約では、一定期間を経過すると地上の利用権が土地所有者に戻るため、安心して土地を貸せるうえ、毎月安定した地代収入を得ることが可能です。

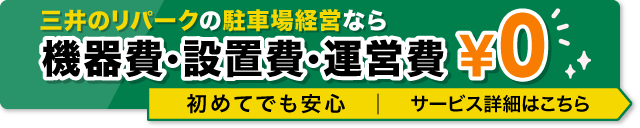
定期借地権と普通借地権の違い
定期借地権と代表的な借地権である普通借地権の違いは、以下の一覧表の通りです。
| 比較項目 |
定期借地権 |
普通借地権 |
| 契約の要件 |
書面での契約に限られる
事業用定期借地権契約の場合は、公正証書契約に限定される |
口頭による契約でも成立する |
| 契約の更新 |
なし
契約期間が満了したら、借地人(借主)は原則として土地を更地にして返還する必要がある |
あり
正当な理由がない限り、土地所有者(地主)は更新を拒否できない
借地人の権利が強く保護されている |
| 契約期間 |
種類によって異なる
一般定期借地権が50年以上、事業用定期借地権が10年以上50年未満となっている |
建物の構造や期間の定めによって異なる
木造のような非堅固建物なら20年以上、鉄筋コンクリート造のような堅固建物なら30年以上
ただし、更新によってさらに長期間契約の存続期間は延長される |
| 土地の利用目的 |
事業用定期借地権は事業用の建物の建築に限られ、一般定期借地権は建物の用途に制限はない(ただし、用途地域など土地にかかる制限の範囲内) |
特に制限はない(ただし、用途地域など土地にかかる制限の範囲内) |
| 建物の取り扱い |
契約終了時に、原則として建物を解体して更地にして返還(明け渡し)する必要がある
ただし、建物譲渡特約付定期借地権は契約満了時に土地所有者が買い取る |
借地人が建てた建物は、借地人の所有物
ただし、借地契約が更新されない場合に借地人が土地所有者に建物を買い取るよう請求できる場合がある(建物買取請求権が設定されている場合) |
普通借地権では、借地人の権利が強く保護されているため、自身の土地であっても正当事由がなければ、土地所有者が土地の返還を要求することが難しいという実情があります。この点が、土地所有者にとっては借地として貸すことの大きなハードルとなる場合があります。一方、定期借地権は契約期間が終了した際に確実に土地が返還されるため、土地所有者にとっては長期的な視点に立った土地運用が可能です。特に安定した収益を確保しながら土地の将来的な活用が保障されるというメリットがあるでしょう。

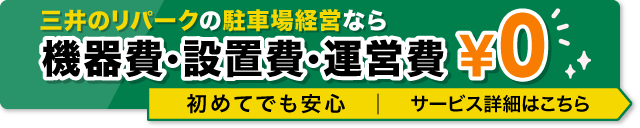
定期借地権の種類
定期借地権には、主に以下の3つの種類があります。
・一般定期借地権
・事業用定期借地権
・建物譲渡特約付借地権
それぞれについて以下で詳しく解説していきます。
一般定期借地権
一般定期借地権は、借地権設定において、建物の利用目的に制限がなく、多様な活用が可能な借地権です。存続期間は50年以上と定められており、主に住宅やマンションなどの居住用として利用されることが多いという特徴があります。契約は公正証書などの書面で締結する必要があり、口頭契約は定期借地契約としては成立しません。
一般定期借地権の契約では、必ずしも公正証書である必要はありませんが、書面での契約が必要です。契約の更新ができないこと、契約期間を延長しないこと、借主による建物買取請求権がないことの3つを特約として契約書に明記します。また、契約満了時には借主が建物を撤去(解体)し、更地にして土地所有者である貸主に返還しなければならないことに注意しましょう。
事業用定期借地権
事業用定期借地権とは、事業のための建物の所有を目的とした借地権のことです。飲食店、ホテル、倉庫、工場といった用途で設定できます。収益目的であってもマンションなどの居住用の建物建築は認められておらず、社員寮や店舗兼住宅も不可とされています。
存続期間は10年以上50年未満と定められており、30年未満か、30年以上かで特約の内容が変わるため、注意が必要です。10年以上30年未満の契約の場合、契約の更新ができないこと、存続期間の延長ができないこと、建物買取請求権がないことの3つを契約の特約として定める必要があり、原則として、契約満了時に土地を更地にして返還しなければなりません。
30年以上50年未満の契約の場合、上記3つの特約を定められるものとして任意となっている点が10年以上30年未満の契約と異なります。なお、契約は必ず全て公正証書で締結する必要があり、それ以外の契約は事業用定期借地権契約としては成立しません。
建物譲渡特約付借地権
建物譲渡特約付借地権とは、契約期間満了時に、借地人(借主・借地権者)が、土地所有者(地主・借地権設定者)に対し、借地上の建物を相当な対価で譲渡する旨の特約を定めた借地権です。契約期間は30年以上とされており、借地権設定上の建物の用途には特に制限がありません。
契約に関しては口頭での締結も法律上可能ですが、後々のトラブルを避けるためには書面で契約を作成するほうが安全といえます。この借地権の特徴は、30年以上が経過している場合、土地所有者が借地人から建物を買い取ると借地権が消滅することです。借地人が建物を買い取ることで更新の必要がなく、権利が確実に消滅するため、定期借地権として分類されます。

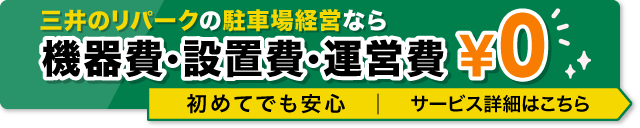
定期借地権を設定するメリット
土地を借地として貸す場合、特に定期借地権を利用して土地活用する際の貸主(土地所有者)のメリットは以下の通りです。
・契約期間満了時に確実に土地が返還される
・土地が更地で返還される
・計画的に土地を貸すことができる
・長期間安定した収入を得られる
・固定資産税などが軽減される
順番に解説していきます。
契約期間満了時に確実に土地が返還される
普通借地権と異なり、定期借地権には契約の更新がありません。契約期間が満了すれば、借地人(借主)は土地を返還する義務があるため、土地所有者(地主)は将来的に土地を確実かつ自由に使用できるようになる点は大きなメリットです。
土地が更地で返還される
一般定期借地権と事業用定期借地権では、土地が更地で返還されることが特徴です。返還後すぐに土地を利用できることに加え、建物買取請求権もなく、建物の取り壊しが条件なので、土地返還時の協議や交渉などが必要ありません。なお、建物譲渡特約付定期借地権の場合、借地権を消滅させるには30年以上経過した後に、建物を買い取る必要があります。建物が十分に使用できる場合には、その建物を買い取ってそのまま土地活用することも可能です。
計画的に土地を貸すことができる
定期借地権の要件により、土地所有者は長期的な視野で計画的に土地を貸し出せます。その理由は、契約期間が満了すれば必ず土地が更地で返還されるという要件により、普通借地権と異なって土地が返還されないリスクを抱える心配がないため、土地を手放したくない場合や将来的な利用計画を考えている場合に適しています。
また、特に一等地などの人気の土地は、普通借地権で貸す場合、超長期的な借地人の権利保護が土地を貸すネックとなり、土地所有者が借地を嫌って、土地がうまく活用されないことが往々にしてありました。しかし、定期借地権とすることで、契約期間満了後には土地が更地で返還され、土地所有者が再び土地を確実かつ自由に運用できます。そのため、土地所有者の不安が解消される一方、借地人は一定期間一等地を利用できるという双方にとってメリットのある土地利用が実現できます。
長期間安定した収入を得られる
定期借地権は、種類によって10年~50年以上の長期契約になるという特徴があり、定められた期間は安定した地代収入を得られることが大きなメリットです。
固定資産税などが軽減される
定期借地権は建物を建てることが前提となりますが、借主が自宅または賃貸用の住宅を建てた場合は、更地と比べて固定資産税や都市計画税の負担が軽減されます。ただし、借主が住宅以外の商業利用の建物を建てた場合は、固定資産税、都市計画税ともに軽減措置が適用されません。
また、相続税については、借地によって土地所有者の土地利用に制限があるため、自用地としての評価額に定期借地権割合と契約期間の残存期間を掛けて計算することが一般的です。そうすることにより、計算上相続評価額が軽減され、相続税額も軽減されることになります。

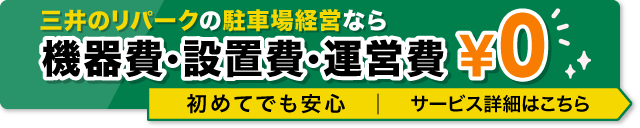
定期借地権を設定する際の注意点
定期借地権を設定する際には、いくつかの注意点を押さえておきましょう。まず、将来的に土地所有者(地主)自身が土地を活用する計画がある場合、長期間にわたって土地を利用できなくなるリスクがあります。定期借地権は契約期間が固定されているため、契約内容を安易に決めてしまうと、後々土地所有者の土地利用計画に制約が生じる可能性があります。そのため、土地の将来的な活用プランを慎重に検討し、契約期間や内容を明確に設定することが不可欠です。
また、契約期間中は当然ながら土地所有者が新たな土地活用を始められません。さらに、契約期間中に土地を売却する必要が生じた場合、その土地は「底地」として扱われるため、市場価値が低下し、所有権と比べて安価でしか売却できません。この点も、土地を長期的な観点で運用する際に考慮すべきポイントです。
さらに定期借地権は、一定の特約がある場合を除き、中途解約が原則認められませんので、注意が必要です。
加えて、定期借地権を設定して土地を貸す場合と、所有する土地にアパートやマンションなどの賃貸住宅を建設して経営する場合では、収益性に差が生じます。定期借地権であっても借地は、長期的に安定した収入を得る点では有効ですが、ほかの土地活用方法と比較すると、収益が相対的に低くなることを理解しておく必要があります。
定期借地権による土地活用が向いている人
定期借地権による土地活用は、土地を手放したくはないが、長期間自分で利用する予定もなく、安定した収入を得たいという方に向いています。以下のようなケースに当てはまる場合は向いているでしょう。
・広い土地を所有しているが、自分で土地活用のための建物などを建てる予定はない
・必ず土地が返ってくることを条件に長期間安定した収入を得たい
・手間のかからない土地活用として借地でもよいが、将来土地は必ず更地で返してほしい
・相続後に相続人が土地を利用できるようなら、土地を貸してもよい
このようなケースでは、定期借地権による借地という形での土地活用が向いている可能性が高いでしょう。

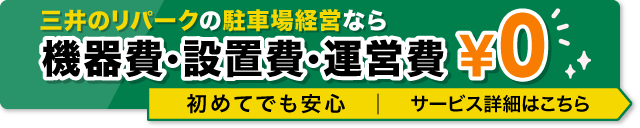
自身の将来設計に合わせた最適な土地活用を
これまで定期借地権について、その特徴や普通借地権との違いなど詳しく解説してきました。定期借地権を利用して土地活用を行う場合には、将来の土地利用計画を長期的な視野で慎重に検討することが重要です。特に、定期借地権の契約は長期にわたるため、迷いや不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。
そのような場合には、定期借地権を活用しての借地と同じように、契約期間が満了すれば、更地で土地が返還される土地活用を検討してもよいでしょう。たとえば、少ない初期費用で始められる土地活用方法としておすすめなのが駐車場経営です。駐車場経営であれば、建物を建てる必要がないため、駐車場としての活用終了後は簡単に更地にできます。
駐車場経営には、自分で経営する自主管理方式、駐車場運営会社に運営・管理を任せる管理委託方式、土地を一括して駐車場運営会社に貸し出す一括借り上げ方式の3つの方法があります。特に、一括借り上げ方式では、駐車場運営会社に土地を貸し出すことで毎月一定額の地代収入を得ることができます。さらに、運営会社によっては事前の告知により比較的短期間でも契約を解除できるケースもあり、柔軟性が高い点も魅力です。
また、一括借り上げ方式では、駐車場の設備導入や維持管理に関する業務を借主である駐車場運営会社が行う場合が多く、土地所有者が手間をかけずに安定した収入を得ながら土地活用が可能です。こうした運営方法は、将来の土地利用計画を考慮しながら柔軟に運用したい土地所有者の方に最適といえるでしょう。
たとえば、三井のリパークでは一括借り上げ方式による駐車場経営も提供しており、最短2ヵ月前の告知で解約が可能です。このため、借地権によるトラブルを心配する必要がありません。さらに、設備導入や管理費用がかからない点も魅力です。
加えて、三井不動産リアルティグループの総合力を生かしたサポート体制により、駐車場経営後も土地活用マッチングサービス「ALZO」を通じて幅広い土地活用の提案を受けることができます。将来設計に合わせた最適な土地活用を実現するために、ぜひご相談ください。
●土地活用マッチングサービス「ALZO」については
こちら※1立地等によってはお受けできない場合もございます。また、建物解体、アスファルト舗装、外構、固定資産税などの租税公課や町内会費はオーナーさまのご負担となります。